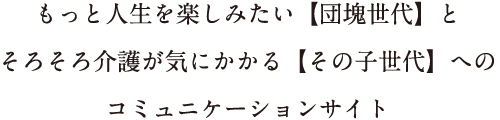認知症の方とケアの専門家が生活を共にする介護施設「グループホーム」。
ここでは一日として同じ日はありません。グループホームで繰り広げられた「心 温まる物語」をご紹介します。

vol.5 世界が変わる瞬間に
これは、私が介護の世界に入って、まだ間もない頃の話。
私は、学生時代に経験した「祖母の死」をきっかけに、この世界に入った。
当時の私にとって、この世界で働くということは、希望に満ちた選択というよりも、「1人でも多くの人を救いたい。」という、半ば使命感に近いものだったように感じる。
自分なりに、それだけの「覚悟」があったつもりだった。
しかし、体裁だけ取り繕ったその覚悟は、いとも簡単に崩れ去ることになる。
現実は思いのほか、過酷で残酷だと思い知ることになった。
私が今の会社に新卒社員として内定が決まり、介護の資格を取るため、ある介護施設に実習に行った時のこと。
そこで私は目の前に映った光景に愕然とした。
寝たきりや、車椅子のおお年寄りが多くを占めるその施設では、排泄介助の時間になると、病院の回診のように職員が居室を巡回し、手際良くオムツを交換していく。
でも、何かがおかしい!
嫌がり抵抗をするお年寄りを尻目に、職員は口角だけ上げられた笑顔で、
「大丈夫ですよ。すぐに終わりますからね。」と声をかけている。
入浴の時間ともなれば、お年寄りを廊下に一列に並べ、まるで工場で見る1つの作業工程のように衣服を脱がせ、身体を洗っていく。
また、施設の中には、常にぶつぶつと独り言をつぶやくお年寄りや、汚物を垂れ流し、徘徊するお年寄り。
寝たきりでほとんど身体を動かすことなく、目も虚ろに1日を過ごすお年寄り。
そこには様々な症状を抱えた人達が存在していた。
これが、私がこれから足を踏み入れようとている世界なのか。
ここで私の「想い」は本当に実現できるのだろうか。
いや、無理だ!
それからの私は、しばらく思い悩む日々が続くことになる。
しかし、時間は何事もなかったかのように過ぎ去り、私はこの「重い」気持ちを引きずったままこの会社に入社し、介護職員として従事することになった。
幸いにも、この会社は、以前自分が体験したような過酷な環境ではなく、人間の尊厳を大切にした温かみのある施設のように感じた。
だが、その時の私にとって、それはもうどうでもいい事であり、この業界にも仕事にも希望を見出せず、自分にもすっかり自信を無くし、いつ辞めようかと考えあぐねる日々が、ただ無駄に過ぎていた。
そんなある日の昼下がり。
施設では食事の時間を終え、団らんの時を過ごしていた。
すると、あるご入居者様が私の方へ歩み寄り、顔を覗き込んでこう言った。
「お兄さん、元気ない顔してるわね。どうしたの?」
私は慌てて「そんなことないですよ。私はほら、元気ですよ。」と笑顔を作ってみせた。
「何かあるのなら、私に話してごらんなさいよ。」
今思えば、自分でも何故そうしたのかは分からない。
気が付けば次の瞬間、私はそのご入居者様に胸の内を全て話していた。
自分にはこの仕事は向いてないのではないか。
自信が持てずこの先どうしたらいいか悩んでいるということ。
自分が抱えている正直な気持ちをさらけ出していた。
しかし、次の瞬間、思いがけない言葉が返ってきた。
「あなたは一生懸命頑張ってるわよ。私はちゃんと知ってるわ。いつも私に枕を持ってきてくれるでしょう。感謝しているのよ。ありがとう。」

そのご入居者様は、足が不自由な方で、いつも杖を使って歩行しているのだが、いつも椅子に座る時など、とても辛そうにしていた。
私はそんな彼女を見て少しでも楽になればと、椅子に座る際には背もたれのクッション代わりに枕をいつも用意していた。
その言葉を聞いた瞬間、思わず涙が溢れてきた。
涙を流したのなんて、一体いつぶりだろうか。
本来、人前で泣くことを恥ずかしいと思っていた私だったが、この時流した涙になぜか清々しさを感じたのを覚えている。
「私をちゃんと見てくれている人がいる。私を必要としている人がいる。」
「私も少しは人の役に立てているのか、私は無力じゃない。」
そう思うことができた。
そしてこれから先の未来に、一筋の希望が見えてきたような気がした。
彼女の言葉に私は救われたのかもしれない。
私は、この仕事を通して気付かされたことがある。
介護とは、一方的に与えたり、支えたりするものではなく、お互いに必要な存在となり、心を通い合わせることが何よりも大切だということを。
私たちはその繋がりの中で、きっと他では得ることができないかけがえのない「何か」を得ているのだと思う。
この会社に入社して5年。
私は今、本社で介護の現場を支援する立場で仕事をしている。
確固たる覚悟や信念があるかというと、正直未だに揺らぐときもある。
現場の課題に直面し、立ち尽くしてしまうときもある。
でも、あれ以来、この世界から逃げたいと思ったことは一度もない。
なぜなら、どんな些細なことでも、私が役に立てる「誰か」がいることを知っているから。
そして、それはきっと私だけが果たすことができる、たったひとつの大切な役割に違いないから。